第001話 ジョージ神父の新たな出発
序章 神父と助手の会話
「ふぅ。白鳥君。ちょっと休憩しようじゃないか。ワシはちょっと疲れた」
「そうですね、神父。ここの整理も後、少しですね」
「そうじゃな」
「吟侍(ぎんじ)君達、今頃、何をしてますかね?」
「さあな、何しとんのじゃろな」
「クアンスティータに関わってたりして」
「口を酸っぱくしてクアンスティータには関わるなと言っておいたが、千年前に予言されておるしの……関わっておるかもしれんのぅ」
「どうされます?」
「どうされますも何も、関わっていたとすれば、ワシごときが何をしようと全く変化はないと思うぞ。何せ、ワシはクアンスティータから逃げた身じゃからのう」
「そう言えば、そうでしたね。という訳であの時、お聞きできなかったお話の続きをお聞きしたいのですが……」
「忘れたわい……」
「忘れたって言われても、気になるじゃないですか。じゃあ、覚えていらっしゃる武勇伝だけでも聞かせて下さいよ。あの時の話じゃなくてもかまいませんから」
「そう、言われてものう……」
「神父なら山ほどあるでしょう」
「冒険の話ならあるにはあるが、ワシはなるべくクアンスティータには関わらないと決めておるからのぅ」
「じゃあ、クアンスティータと関係ない話でもかまいませんよ」
「そうか?じゃが、どんな話をすれば良いのか……」
「何でもかまいませんよ。神父の話なら何でも面白そうですし、地球にいらっしゃった頃のお話でも全然……」
「言ったじゃろ、地球に居た頃は悪党じゃったと」
「なら、クアンスティータを知ってからの冒険でかまいませんよ」
「う、う~ん……」
「何で、嫌がるんですか?」
「何か自慢しとるみたいでのぉ~何となく喋るのはためらわれるのじゃ」
「自慢なんて思っていませんよ。立派な実績です。さあ、話してください」
「じゃあ、ちょこっとだけ……」
ジョージ・オールウェイズ神父は助手の白鳥君にせかされて、また、過去の話をするのだった。
神父はいくつもある武勇伝の中から一つを選択し、話し出すのだった。
第一章 エヴェリーナ神話
俺はジョージ。
ジョージ・オールウェイズと今は名乗っている。
正直、俺は、自惚れていた。
俺がその気になれば出来ないことは何もない――
そう思っていた。
だが、俺は、絶対的な恐怖とぶち当たった。
クアンスティータだ。
クアンスティータは俺が地球で築き上げてきたプライドを全てズタズタに破壊した。
クアンスティータが何をしたという訳ではない。
クアンスティータはまだ、生まれてないのだから。
だが、触れようとした時、想像を絶する恐怖を感じた。
敵うとか敵わないとかの問題ではない。
それまであった価値観全てをぶち壊すような圧倒的な何かを感じた。
それを知ってから、俺は極端に臆病になった。
出来るだけ、クアンスティータに関わらない事を心がけつつも、後進のため、クアンスティータの恐ろしさだけは理解しておこうと調べ上げる事も自身に影響がない範囲でしている。
最強はクアンスティータだとして、№2は誰なんだろうというテーマで調べて行くと、実に様々な存在が名乗りを挙げている。
最強にはなれないが二番目の実力者というのは自分だと主張する存在がかなり多い事が解ってきた。
当然、№2を名乗る者の中でもピンからキリまでの実力差がある。
そういう意味では力の劣る№2を名乗っている者は既に№2ですらないのだろうというのが解る。
だから、今、俺が追っている№2もただのかたりかも知れない。
見当外れの事を探しているのかも知れないが、それでも、完全に無駄という事は無いと思う。
強大な勢力というものの全体的なレベルを知る意味でもこれは必要な事なんだと理解している。
今、俺が追っている神話は、通称、【つぎはぎ神話】や【ゾンビ神話】とも呼ばれている神話で、正式名称は、【Eveliina myth――エヴェリーナ神話】と呼ばれている。
これは、とある男達が惚れた女性、エヴェリーナに捧げるために、すでに終わっている神話をかき集めて、復活させた物語、神話を指している。
神話の寄せ集めという所から【つぎはぎ神話】、
過去の神話を復活させている所から【ゾンビ神話】とされている。
エヴェリーナに神話を捧げた男の人数は3人とも5人とも8人とも言われている。
どの数も信憑性が無く、全く別の人数であるとも言える。
エヴェリーナとは伝説の舞台女優と呼ばれているが定かではない。
なぜ、俺がこの神話を追うことになったかというと、文献にあったエヴェリーナをモデルとしたイラストが気になったからだ。
美しかったからではない。
その表情が何となく気になったからだ。
その文献では男を手玉に取った悪女とされているが、そのイラスト、肖像画からは、どこか物憂げで、とても男を不幸にする女とも思えなかった。
俺が青臭いだけかも知れない。
だが、この神話は現在進行形で、作り続けられている。
この神話が本当ならば、エヴェリーナは有に10億歳を超えている。
だが、それは間違っていると俺は思っている。
世襲制で、エヴェリーナは代々、引き継がれているのだろうと思っている。
そうでなければ、文献毎に顔が劇的に変わっているというのが説明つかない。
俺は、エヴェリーナ神話の文献を十数冊読んだが、そこに書かれている内容と肖像画がこれほど、食い違っている神話は見たことがない。
完全に別人でなければ行動原理が完全に狂っているとしか思えなかった。
それだけ、エヴェリーナという女性は様々な行動を時代時代でとっている。
エヴェリーナに神話を捧げている男達も時代時代で行動が異なっているので、これも世代交代のようなものが行われてきているのではないかと思っている。
俺は、全く手がかりがつかめないエヴェリーナに関わる男達よりもエヴェリーナを追うことにしている。
エヴェリーナの方がいくらか手がかりもあったし、探しやすかったからだ。
探しやすいと言っても、長い間、伝説が残っていれば、偽者の数も多くなってくる。
有名なものに乗っかろうという考えの持ち主はどの時代、どのような状況でも色々と出てくるものだ。
俺は、消去法で、あり得ない者から候補から排除していき、次第に、本物のエヴェリーナらしい人物が居るとされている場所をつきとめていた。
俺が見つけた場所は、宇宙マップにも載っていない辺境中の辺境の森の中にたたずむ洋館だった。
そこは幽霊屋敷と呼ばれ、近づく者はあまり居ないのだが、たまに好奇心で、そこを訪れる者が現れ、二度と帰ってこないという。
捜索に出た捜索隊まで帰って来ないので、何時しか、人々は近づいてはならないヤバイ所として認識されていた。
これは人間に限ったことではない。
神々や悪魔達もこの地に近づくと、二度と戻ってこないと言われている。
どのような存在であっても二度と帰らないというところから、帰らずの森の幽霊屋敷とされている。
行ったら俺も戻れないかも知れない。
エヴェリーナは人間とされているが、実際に、彼女の家族という者は存在しない。
人間である以上、誰かから生まれて来るはずなので、親族が誰も居ないというのはおかしい。
親族が全員死亡して天涯孤独の身になったという情報もない。
ただ、歴史上の途中で突然、出現し、神話の中心になっている謎の女だ。
不気味でもある女なのだが、不思議と惹き付ける何かを持っている。
そこが、この女の特別な力なのかも知れないが、俺は、あえて、この女を捜す事にした。
そこに何が待っているか解らない。
鬼が出るか蛇が出るか――
俺は楽しみでもあった。
何故か、そんなんでもないと思っている自分がいる。
クアンスティータに比べたら、遙かにマシだと思っている自分がいる。
比べる対象を間違えているとも思うが、不思議な安心感を持っている。
クアンスティータに一度でも関わってしまったら、こういう感覚が麻痺するのかも知れない。
俺は帰らずの森に向かった。
そこは、普通の森の様であり、どこか、違和感を持った森でもあるような気がした。
何が違うのかは解らない。
何処が異質なんだか解らない。
森は、静かだった。
シーンという音がぴったりはまるような静けさだ。
小動物が時々現れる。
虫などもいる。
だが、どの生き物もあり得そうであり、どこか不自然な感じのする印象を受けた。
しばらく進む。
だが、どこまで行っても静かな森であり、危険なものは見あたらない。
だが、俺は気づいた。
この森の不自然さに。
生態系から考えるとあり得ない組み合わせの生き物がセットで出てきている。
この星の住民ではないので、正確にこの星の生き物の事が解るという訳じゃない。
だが、長い経験から、この気候ではどの生き物が、別の気候ではあの生き物がという様に、大体ではあるが、生物のあり方のようなものが多少なりとも解るようになっている。
その経験から考えて、どう見てもあり得ない組み合わせが多数、見受けられた。
この事からも、見かけは普通でもこの自然はどこか不自然だという事が解った。
ここの自然はおかしい――
まるで、別の所に居た生物を無理矢理連れてきたかのような状態だ。
だから、俺は違和感を感じたのだ。
それが危険であるとは限らないが、警戒するに越した事はないと気を引き締めるのだった。
俺は更に森をどんどん進む。
だが、同じ所をずっと進んでいる気がする。
方向感覚が狂ったのか?
いや、違う。
この星に合わせて、独自の感覚調整法を駆使しているので、狂っているとは考えにくい。
では、どうなっている?
俺は、一気に、走り出した。
すると、森の方は慌てたかのように、俺に合わせて木が動いているのが解った。
そう――この森は動いていたのだ。
歩いていたから解らなかったが、土地ごと、動き出していた。
この森は生きている。
大きな生命体だった。
俺は、降魔法(こうまほう)を使い、地面に向かって攻撃した。
「ぎゃぎゃああああぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ……」
という声が響き、森が一部消失した。
消失した部分を見ると、かなりの面積だった。
これだけ大きな何かが俺をつけねらっていたのかとゾッとなった。
だが、この程度であれば、神や悪魔ならば、どうという事はないだろう。
他にも何かあるのではないかと俺は推測した。
それまで居た森が消失したので、辺りは何もない荒れ地が広がっていた。
見ると、すぐ近くにあると思われた屋敷が見あたらず、遠くにそれらしきものが見えた。
やはり、何かある。
あの屋敷はどこかおかしい。
俺は進む。
すると、いつの間にか、また森の中に居た。
また、まやかしかと思い、降魔法で攻撃するが、今度は何も起きない。
普通の森に戻ったのか?
それとも降魔法では通じない力を新たな森は持っているのか?
どちらかなのかは俺には解らない。
だが、こうしていても仕方ないので、俺は前に進んだ。
今度もまた静かな森だ。
今度は霧が立ちこめる。
もわっと俺の視界を遮って行く。
だが、この程度の霧に狼狽える俺じゃない。
突破する方法はいくつも知っている。
俺は、その中の一つ、天空視界法を用いる事にした。
これは、視界を上空に持っていく方法だ。
森の中に視点を持っていっては迷うのも無理はない。
だが、上空に視点を持って行けば、目指す目標を見失う事はない。
それ以外にも方法はあるが、とりあえずは、これだけで十分だろう。
俺は、方向を見誤らないように進んでいった。
やがて、目的の屋敷にたどり着いた。
たどり着いてみるとこの屋敷は思っていたよりも小さかった。
遠目に見ている時はかなり大きな屋敷だと思っていたが、近くで見ると拍子抜けするくらい小さかったので少々ビックリした。
「じゃまするぜ」
俺は、屋敷に足を踏み入れる。
不法侵入?
かまうものか。
ここは普通の屋敷じゃない。
人の住んでいる所じゃないんだ。
だったら、そもそも断る必要すらない。
そんな気持ちでドアに手をかけた時、ビリっと来たかと思えば、俺はドアから数メートル下がった位置に立っていた。
何だ?
何が起きたんだ?
俺は気を取り直して再びドアに手をかける。
すると、また、ビリッと来て、気づいたら、俺は屋敷ではない、どこかの場所に移動していた。
屋敷には入れなかった。
俺の目の前には、斜塔が見えた。
斜塔と言えば、地球ではピサの斜塔を思い出すが、それとも違う。
不自然なくらい傾いた塔だった。
その角度は45度を超えている。
恐らくは60度くらい傾いているのではないだろうか。
何時、倒れておかしくない角度だ。
塔の全長は120階建てのビルに相当するくらいある。
これで何で倒れないのかが不思議だった。
これも、何らかの現象なのか?
俺は、理解に苦しんだ。
物事には必ず意味がある――
それが俺の信条だ。
だが、この状態で建っている塔の意味が解らない。
意味のある状態だとは到底思えなかった。
俺は混乱する。
だが、これは俺の理解の範疇を超えた現象であり、俺が理解出来ないだけで、何かしら意味はあるんだと考えた。
そう考えると落ち着いてきた。
不思議な事があっても、以前の時の様にあわてふためく事は無くなってきている。
これもクアンスティータに関わって来たからだとは思うが。
クアンスティータ以上に訳のわからないものはない。
そう思うと、目の前の現象も大したことないと思えるようになっている。
俺は理解出来ないなら理解できないまま、行動しようと決めた。
俺は、塔に入る。
中に入るとそこが塔の中とはとても思えない光景だった。
巨大な大瀑布が目の前に現れたからだ。
とても、120階くらいのレベルの建物に収まるような滝じゃない。
これは、混乱させるためのまやかしなんだと理解した。
訳のわからない光景がどんどん広まっていく内に、対象者は自信がなくなっていくんだと思った。
それが解ると、こんな茶番に付き合っている理由はないと思うようになった。
俺は、この状況からの脱出方法を模索し始めた。
色々試す。
あれもダメ。
これもダメ。
それもダメ。
ダメ、ダメ、ダメ。
どれをやっても失敗ばかり。
だが、俺は諦めなかった。
失敗しても失敗しても繰り返し、何らかの方法を試していった。
やがて、根負けしたのか、俺を取り巻く光景が目的地であった元の屋敷の前に戻った。
しつこくやればなんとかなるもんだな。
俺はそう思った。
俺は屋敷のドアに手をかける。
ぎぃぃぃぃ……
という音がして、中に入る事が出来た。
改めて、
「邪魔するぜ」
と言って、屋敷に足を踏み入れたは良いが、この後はどうしたら良いのか、正直、解らなかった。
エヴェリーナに会う?
だが、俺は、肖像画はいくつも見たが、本人に会っても、それが本物だという確証を持つことが出来ない。
理由は、肖像画がどれも別々の顔をしていたからだ。
このままでは、白人なのか、黒人なのかすら解らない。
人ではないのかも知れない。
見たこともない肌の色をしているかも知れない。
だから、何人か女が現れたとしたら、その中のどいつがエヴェリーナかという確証が持てなかった。
だが、この屋敷には何かある。
何かあると言うことは俺に何らかの不幸が舞い落ちる可能性もあるという事だ。
身の安全を確保したくとも、このよく解らない屋敷の中では、何処が安全で、何処が危険だかは全くわからない。
調べようにも捜査キットが足りない。
さて、どうするか……
俺は思案する。
しばし、考えて、決断する。
この屋敷を一つ一つ、手作業で調べ上げようと。
俺は屋敷の中を見て回る。
見た目はいたって普通の調度品ばかりに見える。
これと言って、不思議な物も見あたらない。
人の気配もない。
誰も居ないのか?
いや、違う。
この屋敷は意志を持っている。
何らかの特別な力が働いている筈だ。
俺はそう確信している。
その確信はすぐに証明された。
屋敷の中の調度品の中には、触れるものと触れないものがあった。
ちゃんと物体として、そこに存在しているものと映像だけで、存在していないものがあった。
何か意味があるのか?
それは解らない。
解らないが、これも俺を混乱させようとしているのか?
一見、不思議じゃないがどこかおかしい。
そんな小さな不安を引きだそうとしている様に俺は思った。
試しに、俺は、触れる調度品を床に落とした。
「おっと失礼……」
といううわべだけの詫びを添えて。
だが、次の瞬間、調度品は元の位置に戻っていた。
他に反応はない。
正直、この屋敷の主は何がしたいのか全くわからない。
少々いらついて来た。
すると――
ぼうっ……とまるで亡霊のように、影が一つ現れた。
その影は、やがて人の形を取り、女の形となった。
俺は、
「……エヴェリーナさんかい?……」
と尋ねた。
すると女は黙って頷いた。
肯定したという事だ。
つまり、この女がエヴェリーナという事なる。
俺は、エヴェリーナに何がしたかったのか尋ねた。
すると、エヴェリーナは、答えなかったが、テレパシーの様なものが俺に伝わって来て、理由を説明してくれた。
エヴェリーナの正体は、創作物だった。
誰かが考え、生み出した存在、それが彼女だ。
様々なイメージが混じって出来たため、様々な見られ方をしていたようだ。
エヴェリーナ神話とはその創作物として誕生した彼女に惚れ込んだ男達が彼女を実在させるために複数の神話を取り込んだ物という事だった。
どんどん膨れあがる神話にやがて創作物だったはずのエヴェリーナも意志を持つようになって来た。
地球で言えば九十九神のようなものだ。
エヴェリーナは力も得た。
だが、それはとても小さな力。
違和感を作り出すというだけのものだった。
俺が惑わされたのもその力によるものだ。
初めから意味など無かったのだ。
エヴェリーナは理想が生んだ存在であるため、心はとても美しかった。
だが、エヴェリーナに狂った男達は違う。
彼女を神聖視する奴らは、無理矢理彼女の神話を盛り立てようと既に終わっている神話をいくつも掘り起こして来て、つぎはぎの様に伝説をつなぎ合わせていった。
そこから、暴走が始まった。
いくつもの神話を食いつぶす、恐ろしい神話に成り下がっていったのだ。
心を痛めたエヴェリーナは男達から行方を眩ます事を考えた。
それが、この違和感の屋敷だった。
彼女は違和感しか作り出せないので、彼女に出来ることは不思議な状況を作って、人の出入りを防ぐ事くらいしか出来なかった。
彼女としては、余生を静かに暮らしたいだけなのだが、彼女を盛り立てようとする男達はエスカレートする一方だった。
勝手に生み出され勝手に盛り立てられる彼女は自身の神話に嫌悪感を抱いている。
消えて無くなる事を望んでいた。
聞いてみれば不憫な話ではある。
自らを生んだ神話の消滅を願っているのだから。
俺は、彼女をそっと抱いた。
「俺が終わらせても良いか?」
エヴェリーナは黙って頷いた。
それを聞いた俺は、エヴェリーナにまとわりつく男達と戦う決意を決めた。
彼女からまとわりついている男の人数を聞く。
すると、彼女の口から1人だという事を聞いて、驚いた。
複数いると思っていたからだ。
実際には、その1人の男が色んな者を雇って複数いるように見せかけているだけだというのが解った。
1人だという事が解れば、後は、そいつをぶちのめすのみ。
俺は、その男の名前を聞いた。
その男の名は、Vilhelm―― ヴィルヘルムという。
ウィルヘルムと対する事になった俺は戦闘のための準備をする事にした。
敵は神話を作り上げる男――
元々は、俺もそれを目指していたので、言ってみれば、俺のやろうとしていた事の先輩という事になる。
神話を利用する事にかけて言えば、向こうの方が何枚も上手だろう。
だが、そんな事は知ったこっちゃない。
俺が進もうとしている事の妨げになるようなら排除していくだけだ。
俺は、エヴェリーナの屋敷に新たな結界を張った。
エヴェリーナの行方を眩ますのはもっと地味な結界の方が良い。
今までのでは悪目立ちしすぎる。
恐らく、ウィルヘルムという男であれば、容易にここがエヴェリーナが潜んでいる所だと気づくだろう。
だから、俺はエヴェリーナの気配を分散させ、移動したように見せかけた。
その上で、エヴェリーナの気配をそれまでとは全く異質なものに変化させた。
俺の推測が正しければ、これで、ウィルヘルムはエヴェリーナの気配を見失うはずだ。
エヴェリーナの偽の気配を移動させてからしばらくして、俺はエヴェリーナを連れて屋敷を出た。
その上で、別の場所で、更に彼女の気配を変えて、また、別の場所に移動し、更に別の場所でまた気配を変えるという行為を何度か繰り返した。
これで、よっぽど探知能力に優れている存在でもない限り、追ってはこれないはず。
その場にエヴェリーナを残し、俺はその場を離れた。
逃げてばかりでは何にもならないからだ。
エヴェリーナから聞いたウィルヘルムの情報を元に、こちらから探索する。
とは言っても、この場から直接追ったのであれば、逆探知により、エヴェリーナの所在が解ってしまう。
俺は更に何カ所もまわり、エヴェリーナの所在地をぼかしてから、改めて、ウィルヘルムを追い出した。
エヴェリーナの情報によれば、ウィルヘルムという男は、蘇生や復活術に関する能力が飛び抜けて高いという事が解っている。
その力を駆使して、終わってしまっていた伝説や神話を呼び起こしてきたのだ。
ならば、その力に対しては特に注意をはらわねばならないだろう。
どんな厄介な神話を呼び起こされるか解らないのだから。
だが、俺に言わせれば、どんな神話だろうと、一度は終焉を迎えた神話だ。
それが終わる切っ掛けというものが必ずあるはず。
それを掴めば、神話に対する対抗策というのも見えてくる。
俺は、ウィルヘルムの住む星を目指した。
奴は、エヴェリーナの住んでいる星の隣の惑星に住んでいた。
ここを拠点として、様々な星を渡り、眠っていた神話を呼び覚まして、自身の神話として取り込む事を行ってきていた。
ウィルヘルムによって加工された神話は新たなるエヴェリーナ神話としてリニューアルされ、生まれ変わる事になる。
それで、奴は今、新たに持ってきた神話の加工の真っ最中って訳だ。
だからこそ、エヴェリーナに対して、何のアプローチもかけて来なかったのだ。
エヴェリーナに対しては普段、色んな神話のプレゼント攻撃という事でアプローチをしているようだ。
俺は、エヴェリーナ神話を測定器にかけて計っていた。
ギリシャ神話を1.000とするエヴェリーナ神話の数値は12.893という数値を出していた。
以前の測定器では10.000までしか計れなかったが、クアンスティータと関わるようになってから桁がまるで足りないとして、改良したのだ。
それにより、その1000倍、10000.000まで計れるようになっている。
それでも、ファーブラ・フィクタ神話の数値は全く計れないだろうが。
俺が、エヴェリーナ神話に目をつけたのも測定値が10.000を超えていたからだ。
とは言え、12.893は低すぎる。
クアンスティータの関わるファーブラ・フィクタ神話は別格としても、№2の神話がこの程度の数値とは考えにくい。
ただ、余り、高すぎると俺の技量がついていけないから、この丁度良い数値のこの神話を俺は選んだだけだった。
だが、今、計ったら、数値が12.926に上がっている。
数値全体からすれば僅かな違いだが、それでも規模としては、神々が数柱は増えたような数値を示している。
この神話は成長しているんだ。
いや、膨張しているのかもしれない。
人間に例えれば、スマートだったボディーに筋肉や脂肪を次々と増やしている感じだ。
すでに、この神話には長い時をかけて、把握しきれない程の神話が塗り重ねられている。
手がつけられなくなる程の巨大な勢力になる前に何とかした方が良いだろう。
俺は、ウィルヘルムの惑星の辺境に降り立った。
そこから、奴の住む場所までの距離は、およそ、数千キロは離れている。
少々離れすぎだ。
だが、それには狙いがある。
この星は神話の加工場でもある。
つまり、星の至る所に、その爪痕が残っているはずだ。
俺は、ウィルヘルムにたどり着く前に、エヴェリーナ神話の事を少しでも理解しておこうと考えた。
途中で利用できる物は再加工して、俺の所持品として使わせて貰おうと考えている。
俺は茂みに隠れながら、進んだ。
第二章 神官サドマゾとの死闘
茂みを進んでいくと、開けた場所に出た。
そこは、どうやら古代の闘技場の様になっているらしい。
人――かどうかは解らないが、気配がした。
数十名はいる。
神官のような女が一名。
それを取り囲むような形で数十名の配下らしき存在がちらほら――
それ以外には罪人?を思わせる風貌の男達が十数名いた。
罪人風の男の一人が叫ぶ。
「本当だな、お前を倒せば見逃してくれるんだな」
どうやら、捕まっていた者達が解放してもらうには、神官の女を倒すというのが条件らしい。
神官の女は答える。
「この神官サドマゾ、二言はない。我を倒せば解放しよう」
サドマゾと名乗るこの神官の女は何者なのだろう?
見たところ、岩を削って作ったと思われるいくつかの玉があり、そこには魔法陣らしきものが描かれている。
推測するに、サドマゾは召喚師のようだ。
魔法陣の書かれた玉から、何かを召喚するタイプの戦い方をするのだと推測できる。
罪人風の男達がサドマゾを取り囲む。
見たところ、サドマゾの配下と思われる数十名は何の手も出さないようだ。
サドマゾを取り囲む罪人達の更に周りを取り囲んでいるから、恐らくは、サドマゾと戦うのならば手は出さないが、そこから逃げだそうとすると捕まえるか、手を出してくるのだろう。
罪人達を逃がさないための配置であると言える。
「サドマゾが命じる。咎人を縛りし鎖よ、崩れ落ちよ」
とサドマゾが言う。
すると、罪人達を縛り付けていた鎖がドロドロに溶けて落ちた。
これだけ見ても解る。
恐らく、罪人達が束になってもこのサドマゾには勝てない。
殺される――
そう思った。
罪人達が一斉に襲いかかる。
だが、サドマゾは動じない。
「サドマゾが命じる。いでい、ザンバ」
と唱えると、魔法陣玉の一つから、黒い馬の様な存在が現れた。
でかい。
ざっと10メートルはある。
「ブルルルルルル……」
ここからでも解る。この馬の戦闘力はかなりある。
「おおお……」
「うま?……」
罪人達が驚く。
「サドマゾが命じる。そこの二人を殺せ」
サドマゾが命令すると、ザンバは狂った様に暴れ出し、彼女が指した二人を跳ね飛ばした。
たまらず、他の罪人達は逃げまどう。
罪人達もそれなりに特殊能力を持っているらしく、時折、サドマゾやザンバに攻撃するのだが、
「サドマゾが命じる。いでい、ハンテン」
とハンテンと呼ばれた三日月に手足が生えたような怪物が現れ、その特殊能力を悉く無効にしていった。
ザンバやハンテンだけじゃない。
要所要所で、怪物を召喚し、罪人達を追い詰めていった。
感想を言わせて貰えば、これはバトルじゃない。
殺戮行為だ。
罪人達は為す術無く、サドマゾの召喚術の前に翻弄され、やがて絶命して言った。
罪人達が全員死亡すると、サドマゾは、
「お前達、食って良いぞ」
と配下に命令する。
すると、配下達は我先にと罪人達の遺体に群がり食べ始めた。
気の弱い者が見たら失神するような凄惨な光景だった。
君子危うきに近寄らずという言葉もある。
俺はやり過ごして、行こうと思ったのだが、
「そこの男、解っておるぞ」
と声をかけてきた。
隠れていたつもりだが、どうやら、サドマゾにはお見通しだったようだ。
罪人達の始末の仕方を見ている限り、まともに話の通じる相手とも思えない。
だったら、やるしかないか――
俺はそう考えた。
召喚師くらいなら、何度も手合わせはしている。
対して珍しい術だとも思えんし、やってみるかと思った。
俺は地球時代、様々な術を習得してきたんだ。
こんな残虐な女ごときに遅れを取るつもりはない。
そう思って戦闘態勢をとった。
だが、サドマゾは、
「いい男だな……顔がという意味ではない。その精力がだ。長い時を生きてきたその胆力は素晴らしい。我は抱いてみたい……」
と言ってきた。
俺は一瞬、ゾッとなった。
俺は男だし、サドマゾは女だ。
お互い認めればそういう関係になってもおかしくはない。
だが、そういうのとは違う。
得体の知れない存在に蹂躙される。
そんな不気味な気配が俺を襲った。
冗談じゃない。
こんな得体の知れない女と関係を持てるか。
俺は断固、拒否した。
するとサドマゾは、
「そうか、それは残念だ。永遠の快楽を与えてやれたのだが……」
と言ってきた。
俺からしてみれば、そういう所が得たいが知れないから嫌なのだが、そういう気持ちはくんで貰えないようだ。
俺は、自身の経験から出せる限りの奥義、術を組み合わせて、サドマゾに対抗した。
だが、ハンテンの力で術が思うように作動しない。
俺は、手を代え品を代え、術を試した。
だが、その全てが通じない。
どうやら、術の組み方が根本的にこの女のものと俺のものとは全く異なるようだ。
逃げるか?
俺の頭はそれがよぎった。
だが、敵の攻撃もサドマゾが思うようには作動していないようだ。
あの女にも多少動揺しているのが伝わってくる。
戦いにくいのは俺だけではない。
それが解っただけでも十分だった。
どうにかして、先に、敵に有効な手段を見つけた方が勝つ。
そう思った俺は、今までの常識を覆すやり方を試していった。
かなり、当てずっぽうだったのだが、先にやったのが良かったのか、敵への有効打に先にたどり着く事が出来た。
サドマゾの術式と俺の術式はまるで水と油のように合わない。
だとすれば、俺が普段やらないような術式を組めば良いのだという結論に早く気づく事が出来た。
答えに先にたどり着いたので、俺は、サドマゾの術式を全て無効にする事が出来た。
あの女の周りに陣取っていた魔法陣玉もただの岩の塊と変わらなくなった。
観念したのか、サドマゾは自らの死を選択した。
それが何ともえぐい。
自らの身体を食いだしたのだ。
その姿は正直みて居られなかった。
凄惨な場面を散々見てきた俺でさえ、目を背けたくなるような光景だった。
吐かなかったのが不思議なくらいだ。
だが、これで、俺はサドマゾを退けた。
サドマゾが死亡したら、サドマゾの配下が僅かに残ったサドマゾの身体を食いだしたので、思わず、俺はこいつらも始末した。
行動に吐き気を覚えたからだ。
サドマゾは下したが、これは、まだ、エヴェリーナ神話のごく一部でしかない。
いや、ごく一部にも入っていないかも知れない。
ウィルヘルムによって無理矢理、一つの神話に閉じこめられている神話のねじれや歪みが末端にまで浸透しているのを俺は感じた。
俺はさらに先に足を進める。
再び、茂みに身を潜めながらの進行だ。
第三章 後継者に向けて……
どのくらい進んだだろうか……
俺はまた、開けている場所に出てきた。
そこは、一面、カビの生えている大地だった。
ここには何があるか解らない。
ただ、カビがびっしりと大地にこびりついていた。
ふ、と上空を見上げると無数のドラゴンが。
いつの間に――
そう思ったが、次の瞬間、悪魔の軍勢に変わる。
どこかで見たような光景だったと思ったが、エヴェリーナの屋敷で体験済みだった。
よく解らない情景を作り出す力はここで生まれたのだと思った。
すると、これは良くできた幻か――
そう思ってしばらく立ち止まっていると、
ズシン、ズシンと大きな地響きが立つ。
見ると、遠方から巨人が数名こちらに向かって歩いて来ているのが確認出来る。
これは厄介だと俺は思った。
特別な力を持っている相手であれば術を駆使して対抗も出来るが、相手が巨人であった場合、その巨体を利用した力任せの攻撃に出られたら俺は一溜まりもない。
純粋な力では、巨人のパワーには勝てないのだから。
その巨人が数名――数えると8名確認出来る。
8対1の不利もあり、がたいの不利もある。
俺は、この場に居ては不味いと思い、身を隠す事にした。
カビの生えた土地ではなく、そこから少し外れた位置に身を潜める。
すると、巨人達は、カビの生えた土地に立ち止まり、そして、カビをなめ回す。
どうやら、このカビは巨人達の食料となっているようだ。
よく見ると、耳が長い。
エルフの要素も持っているかも知れない。
巨人達は、その場で談笑する。
声が響き渡る。
黙って聞いていると鼓膜が破れそうだ。
俺はたまらず、その場を離れる。
それが見つかったのか、
「おい……」
と巨人の一人が言った。
別の巨人が、
「どうした?」
と聞く。
「いや、何か動いたような……」
「気のせいだろう」
「そうかもな」
「それよりもどうする?」
「ウィルヘルムか……?」
「そうだ。あいつの行動は目に余る」
「そうだ。あいつはまた、俺達の仲間を殺した」
「もう、許せん」
「いい気になっている」
「ひねり潰してやろう」
「そうだそうだ」
なにやら、物騒な相談をしているようだが、どうやら、ウィルヘルムの仲間という訳ではないらしい。
むしろ、ウィルヘルムに対して、敵意を持っているようだ。
巨人達の話を聞いていくと事情が大体わかってきた。
この星は元々、この巨人達が住んでいた星だったらしい。
そこへ、ウィルヘルムがやってきた。
そして、他の星の神話を手に入れて来ては、この星で復活させて、この星の巨人達と戦わせているらしい。
50億程いた巨人達も、今では10数万名にまで数を減らしているらしい。
度重なる実験戦闘で、星は荒れ果て、巨人達は、カビを舐めて飢えをしのぐようになっているらしい。
だとすれば、この星の巨人達と協力してウィルヘルムに挑もうとも考えたが、この巨人達は、大きい。
ざっと見て、平均30数メートルはあるだろうか。
この巨人達と行動を共にすれば、戦力にはなるかも知れないが、目立ちすぎる。
ウィルヘルムがどんな力を持っているかも解っていない状態で、目立つのは命取りにもなりかねん。
巨人達との交渉に使える材料も無いし、交渉ならば、後でチャンスもやってくるだろう。
ならば、今、この巨人達と行動を共にする必要はないな。
俺は、そう判断して、巨人達と関わらずに、その場をこっそりと離れて行った。
幸い、結構、物事に無頓着な巨人達だったらしく、俺の動きを気にするでもなく、宴会を始めて騒ぎ出した。
ここに居ては目立つ。
俺はそそくさとその場を離れた。
だが、巨人達からある程度の情報は聞けた。
それだけでも十分な成果と言ってよかった。
俺は、歩を進める。
大分、進んだ。
とは言え、歩きでは、限界がある。
まだ、目的地には遙かに遠い道のりが残っている。
そこで、俺は、地球から失敬してきた魔法の絨毯を用意した。
これで、飛んで行くことが出来る。
とは言え、それ程、早く飛べる訳ではないから、それでもかなりの時間はかかるし、上空に行きすぎると逆に目立つから、地面すれすれの低空飛行で進んでいく事になる。
だから、障害物も多く、なかなか思うようには進まなかった。
障害物も多かったが、出会う者も多かった。
俺は、ウィルヘルムの居城へと進む途中で様々な存在と出会っては別れて行った。
時には話を聞き、時には戦闘にもなった。
わかり合った者も居れば、わかり合えず命の取り合いをした相手も少なからず出た。
戦闘が重なれば、戦闘スキルもアップしていく。
もう十分、成長しきっているので、あまり、成長する事はないなと思っていたが、まだまだ、成長の余地は残っていたようだ。
俺は、地球時代よりもかなり、戦闘スキルをアップさせた。
とは言っても、地球時代を1とすれば、100に満たない成長だ。
これでは、クアンスティータ辺りと比べたら、全く変わってないのと一緒に映るだろうなとは思う。
自信過剰になってはならない。
いくら成長しようとクアンスティータには全く届かない。
それは、嫌と言うほど解っているつもりだ。
最強は目指さない。
目指しても虚しいだけだからだ。
上には上、とんでもなく、途方もなく上は居る。
それは、クアンスティータに限った事ではない。
クアンスティータの周りにはそういうのはゴロゴロいるだろうし、クアンスティータを恐れる存在の中にも、俺から見たら雲の上の実力者というのは腐るほどいるはずだ。
俺は、様々な冒険を経て、自分の力の小ささを知った。
どんなに頑張っても俺は不死身の相手と戦えば、いずれやられてしまうだろう。
1000年の後に現れるらしい、俺の後継者は不死身の相手をあっさり倒せる力の持ち主らしいが、俺は、出来れば不死身の相手とは戦いたくはない。
その出来の良すぎる後継者を持ってしてもクアンスティータには全く歯が立たないらしいから、クアンスティータは比べるだけ間違っているというのは理解している。
クアンスティータ関係は余所に置いておくとして、問題は俺のレベルで何処までの存在と関われるかの見極めはどうするかという所だな。
俺の手に負えない様な相手はどうしようもないから、せめて、俺でも何らかの抵抗が出来るくらいのレベルの相手と関わっていこうと思っている。
エヴェリーナ神話は俺が手を伸ばせば届くと思っている。
数値として、13.000に満たないレベルの神話だ。
これくらいなら、まだ俺でも何とかなる――そう考えている。
だから、俺は進む。
俺でも通じると思うからこそ、希望を持って、ウィルヘルムと戦う決意をしている。
エヴェリーナのため?
いや、違うな。
確かに、エヴェリーナの事は気にはなるが、妻に娶りたいとかそう言った感情は持っていない。
相手は、元々架空の存在なのだから。
それよりは、俺の今のレベルを知りたい。
理解して、どこまでのレベルに通用するか試してみたい。
これは後々の後継者達にも伝えようと思っている事だ。
自分より格上の存在に挑もうとする後継者達に対して、俺はどのようなアドバイスをしたらいいか?
それは、やってみないと出来ない。
解らない。
だから、強い相手に挑む。
地球時代の俺は、圧倒的な力を持ち、上からの目線で敵となる相手に向かっていった。
だが、それではダメだ。
格上相手にそれは通じないからだ。
格下の存在は格上の相手と戦うためにどのような準備をしていかなければならないか。
それを実戦で身につけて行かねばならない。
自分が出来なかった事を後継者達に押しつける真似は出来ない。
実際にやってみてから、こういう場合はどうしたら良いというアドバイスが出来るようになるはずだ。
勇気と無謀は似ているが異なっている。
どうあがいても通じない相手には挑むべきではない。
全く敵わないと思ったら、退く勇気というのも必要な事だ。
これも、俺は、実体験として、身につけて行こうと思っている。
難敵に挑む勇気と退散までの見極め――
この二つの技能を俺はこれからの冒険を通して、身につけていく事になるだろう。
この冒険はまだ、始まったばかりだ。
俺の後継者は1000年後に現れるという。
まだ、1000年もある。
もう、1000年しかないとも思えるが、俺は前者を取る。
後継者達に俺はどう語っていくんだろうな。
今から楽しみだ。
それを楽しみながら、俺は、ウィルヘルムの居城に向けて、更に進んで行った。
第四章 それから……
「それからどうなったんですか?」
「いや、何というか……」
「また、途中で終わらす……」
白鳥君はまたしてもあきれ顔だった。
ジョージ神父が話を途中で区切ったからだ。
「しかしのぅ、休憩時間に話すようなものではないしのぅ。話すと凄く長くなるんじゃよ」
「じゃあ、今度はちゃんと時間を取って聞かせてくださいよ」
「聞かせると言われてものう……最終的にはワシは生き残っている訳じゃから、負けてないんじゃよ」
「でしょうね」
「最後はウィルヘルムを倒して、めでたしめでたしという訳にはいかんかのぅ?」
「いきませんね。また、不完全燃焼ですよ」
「ウィルヘルムは神話の合成を得意とした奴じゃった。じゃが、オリジナリティーに欠けるところがあってのぅ……」
「ふんふん、それで?」
「過去の文献などをひもといていってのぅ――1つ1つを元の神話に戻していった。それでしまいじゃ」
「盛り上がりそうな所を一切聞いておりませんが」
「途中、寄り道とかしてのぅ。10年くらいかかったんじゃよ、エヴェリーナ神話の解決は……」
「そこを聞かせて下さいよ」
「複雑に入り組んだ話になったから、話すのが面倒なんじゃよ」
「そうやって、また、面倒臭がる……」
「この話で重要なのは、ワシが後継者である吟侍達に向けて、色々、教える事を自ら学んでいく決意をしたという所じゃ。後はオマケのようなものなんじゃよ」
「バトルシーンが殆どないじゃないですか」
「ワシ、バトルきらいじゃもん」
「良いから聞かせてくださいよ」
「さて、休憩時間も終了じゃ。そろそろ、また、働いてもらうぞ、白鳥君」
「そうやってまた、はぐらかす……」
午後の休憩時間も終わり、ジョージ神父と白鳥君は、再び働きだすのだった。
ジョージ神父はスッキリしていたが、白鳥君はモヤモヤしたままだった。
部屋の片付けは続く。
続く。
登場キャラクター説明
001 ジョージ・オールウェイズ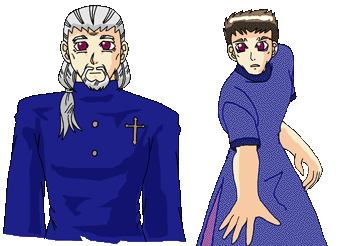
本作の主人公。
【ファーブラ・フィクタ】の主人公、吟侍達の育ての親であり、ヒロイン、カノンのメロディアス王家の最初の妃、クラシックをホムンクルスとして作り出した存在。
地球時代、様々な名前と姿形をとって九千年の時を過ごしたが、追い出され、復讐を誓ったという過去を持つ。
現在は、孤児院、セントクロスで神父をして、孤児を育てている。
冒険の末、七番の化獣(ばけもの)ルフォスの核を持ち帰る。
クアンスティータ、クアースリータに対して、恐怖を抱く。
普段は孤児院を運営する神父として生活している。
002 白鳥 健三(しらとり けんぞう)
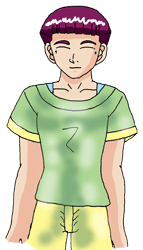
ジョージの孤児院に手伝いに来ている助手。
セカンド・アースの勇者、吟侍に憧れを持っていて、その恋人、カノンに密かな恋心を持っている。
少しでも二人に近づきたくて孤児院セントクロスに手伝いにやってきた。
暇をもて余してはジョージの武勇伝を聞きたがる伝説オタクでもある。
003 クアンスティータ

【ファーブラ・フィクタ】神話において最強とされる13番の化獣(ばけもの)。
誕生させていたら神や悪魔側に勝利は無かったとされている。
一番のティアグラが過去を司り、七番のルフォスが現在を司り、十三番のクアンスティータが未来を司るとされている。
その生誕と正体には多くの謎が残されていて【化獣の絵本】では心優しき少女、【レインミリー】の生まれ変わりとされている。
神話の時代、母の【ニナ】が必要以上の栄養を取ってしまい、誕生には七名の母体が必要になってしまったため、誕生することは無かった。
だが、誕生させていたら全てが終わりだというどうしようもない程の恐怖だけは神や悪魔側に深く刻みつけた。
クアンスティータが母、【ニナ】から受け継ぐ予定だった宇宙世界の数は二十四と他の化獣をも圧倒する。
七つの本体、十七の側体を持つとされていて、更にその奥?が存在するとも言われている。
誕生すれば、間違いなく最強の座につく存在。
004 エヴェリーナ
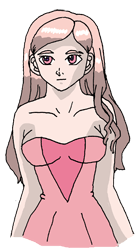
ジョージ神父が千年前に挑んだ神話の一つ、エヴェリーナ神話の中心人物。
架空の存在であり、様々なイメージが複雑に合わさって存在している。
違和感を作り出すという力を持っているが、とても小さい力。
自分のために、次々と終わった神話が掘り起こされているのを悲しみ、自身の消滅を望んでいる。
ウィルヘルムという男から逃げている。
005 ウィルヘルム

エヴェリーナを神聖視し、彼女のために、次々と終わった神話、伝説を掘り起こしている男。
蘇生術や復活術などが、他の存在の追従を許さない程、飛び抜けて優れていると言われている。
エヴェリーナを作り出した産みの親でもある。
006 神官サドマゾ
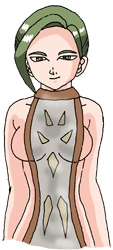
ウィルヘルムが神話の加工に使用している星にいる女神官。
召喚術を得意とし、ザンバやハンテンといった数々の怪物を召喚し、敵に襲いかからせる力を持つ。
グールの様な配下を持ち、ジョージに敗れた後は、自身を食い、自決して果てた。
見かけは女性だが、中味は、もっとおぞましい何か。